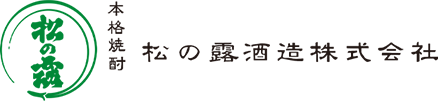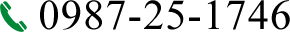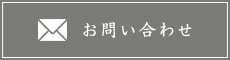焼酎ができるまで
Step.01製麹
麹は蒸した米や麦などに麹菌と呼ばれるカビの一種を約2日間かけて繁殖させたものです。
焼酎用の麹には黒麹菌と白麹菌があります。
黒麹菌はもともと泡盛用の麹で、コクのある焼酎に仕上がるといわれております。
一方、白麹菌は黒麹菌の突然変異株で、口当たりがソフトな焼酎になるといわれております。
黒麹菌や白麹菌はクエン酸などの酸をよく生産し、焼酎もろみを強い酸性にして雑菌汚染を防止いたします。


Step.02一次仕込み
酒造りに欠かすことのできない「発酵」。
焼酎の発酵は主に、「一次もろみ(酒母)」と「二次もろみ(本もろみ)」に分けて行われます。
一次仕込みは麹と水に酵母を加えて一次もろみを造る作業です。
約1週間かけて発酵させます。
目的は純粋で強い酵母を培養して、二次もろみに必要な酵素とクエン酸をつくることです。


Step.03主原料処理
焼酎の主原料となる「穀類」や「いも類」の処理を行います。
たとえば、原料が「甘藷(かんしょ)」となる場合は、甘藷の傷んでいるところや両端を切り取り、ある程度の大きさになるようカットしてから、蒸し器に入れます。


Step.04二次仕込み
一次もろみに、主原料と水を加え発酵させます。
約2週間の時間をかけ、ゆっくりと行う工程です。
そうすることにより、甘く芳醇な二次もろみに仕上がります。


Step.05蒸留
蒸留釜に二次もろみを入れ、蒸気を吹き込んで加熱いたします。
もろみが沸騰しアルコールが蒸気となります。
これを冷まし液体になったものが原酒です。
この際に、アルコールと一緒に微量の香りなどの成分が原酒に溶け込みます。
本格焼酎独特の芳香や風味は、これらの成分によって醸し出されます。


Step.06貯蔵・熟成
蒸留後、出来上がった原酒は貯蔵タンクで貯蔵・熟成させます。
その後、アルコール度数を調整したものを瓶詰めして出荷いたします。
この熟成の期間によっても焼酎の味や風味が変わっていきます。
大きく分けると、「初期熟成(3~6か月)」「中期熟成(6か月~3年)」「古酒化期(3年以上)」の3つに分けられております。

以上の工程を経て、焼酎は皆様のお手元へ届けられます。
ご紹介したのは、ごく一般的な方法ですが、焼酎は「主原料」「製造工程」「熟成期間」などによって、さまざまな味わいを生み出せるお酒です。これからも、皆様にご満足いただける焼酎造りができるよう精進して参ります。